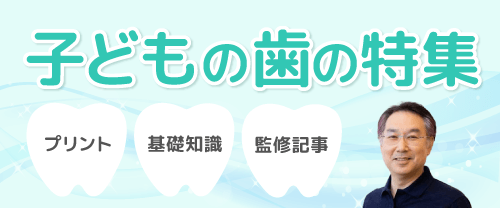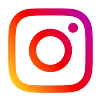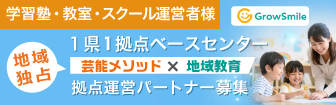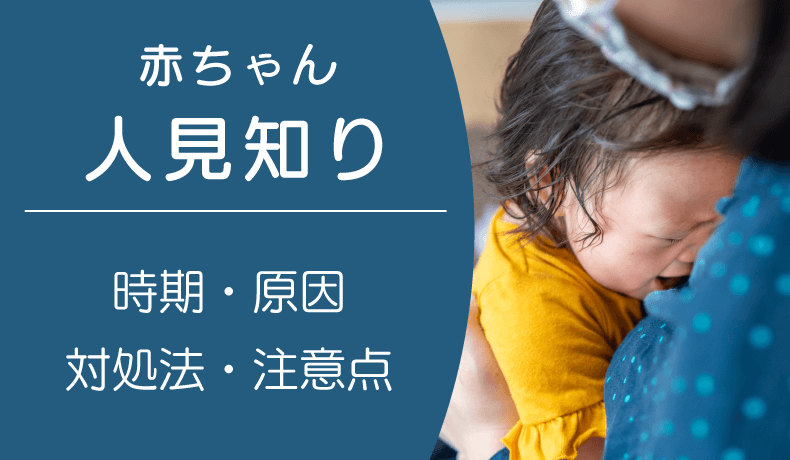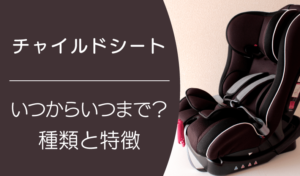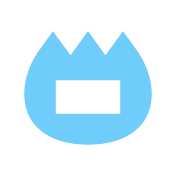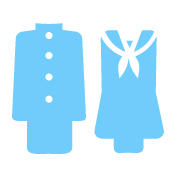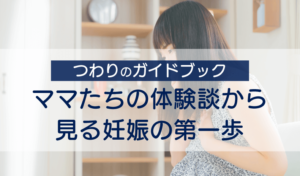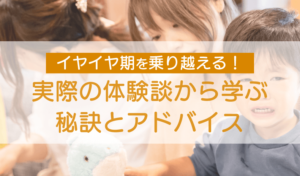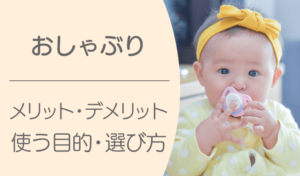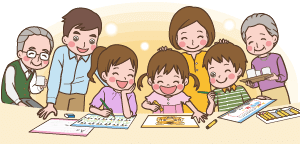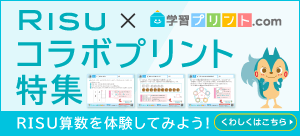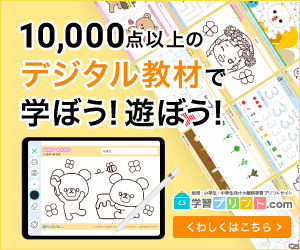赤ちゃんのパパ見知りとは?起こる時期や原因と対処方法

「パパ見知り」という言葉、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
つい最近まで、パパにニコニコ抱っこされていたはずなのに、何ヶ月か後に急にパパの抱っこを嫌がるようになった。
これが「パパ見知り」です。
パパ見知りが始まると、ママと一緒の時はご機嫌でパパにもニコニコしているのに、パパが抱っこしようとするとママじゃないとダメだと大泣きし、パパが拒否されやすくなります。
生まれてすぐの頃にはパパを嫌がるようなことはなかったのに、どうして突然パパを嫌がるようなことが起きるのでしょうか?
そして、パパ見知りが始まると、パパの心は「父親なのになぜ自分ばかり嫌うのか」と悲しく感じるようになり、とてもつらい気持ちになるパパも多いのではないでしょうか。
ママが家事をしている間に抱っこしようとしても泣かれてしまうことが多くなると、ママばっかりが抱っこやお世話をする時間が増えてしまい、ママも負担になります。
ママが病気になった時など、パパが赤ちゃんのお世話ができなければ大変です。
そんなパパ見知り、赤ちゃんは決してパパが嫌いなわけではないのです。
パパ見知りには実は原因があり、その原因を理解して対処方法さえ分かっていれば、赤ちゃんとの関係を築いて安心してコミュニケーションもとることができます。
そこで、赤ちゃんのパパ見知りはどのようなもので、起こる時期や原因と対処方法について見ていきたいと思います。
目次
赤ちゃんのパパ見知りとは?

パパ見知りとは?
赤ちゃんの「パパ見知り」とはどのようなものなのでしょうか?
赤ちゃんが、パパに対して人見知りをすることを「パパ見知り」と言います。
パパ見知りは同じ家族でも、ママといる時にはニコニコしていた赤ちゃんが、パパが声を掛けたり、抱っこをしようとしたり、なかには近づこうとしただけで大泣きしてしまうこともあります。
まるで、パパが全然知らない人のように赤ちゃんが泣くと、パパも悲しい気持ちになります。
そして、今まで積極的に育児に参加していたパパほどショックで、パパ見知りを機に、育児から遠のいてしまうパパもいるかもしれません。
パパ見知りって昔はなかったの?
この「パパ見知り」という言葉は、パパが子育てに積極的にかかわるようになったことから生まれた言葉で、ここ20年ほどで雑誌などで話題になった言葉なのです。
それまでは「男性は外で働いて、女性は家庭や子育て」という考えで、恐らくパパ見知りなんて問題になるような状況にもならなかったのでしょう。
それが、最近ではパパが育休を積極的に取得して「イクメン」なんて言葉まであるほどに、赤ちゃんのお世話に参加するパパが増えてきました。
そこで、赤ちゃんに人見知りをされるということが問題になってきたのでしょう。
「パパ見知り」が気になるのは、家庭のなかで積極的に子育てに関わりたいと言うパパの姿勢からくるのでしょう。
パパ見知りが起こる時期や原因

では、パパ見知りが起こる時期はいつごろで、パパ見知りの原因は何なのでしょうか。
パパ見知りが起こる時期
パパ見知りが起こる時期は、一般的に生後5ヶ月頃~7ヶ月頃に始まると言われています。
パパ見知りは人見知りの一種なので、人見知り同様に個人差があります。
早い子は生後3ヶ月頃から始まる赤ちゃんや、1歳を過ぎてから始まる赤ちゃんもいます。
そして、もちろんパパ見知りをしない赤ちゃんもいます。
いつまで続くかですが、これもまた個人差があります。
2、3ヶ月で終わる赤ちゃんもいれば2~3歳ころまで続くこどももいます。
一度治まったパパ見知りが、時間が経ってから再度繰り返すこともあります。
「パパ見知りはいつからいつまで」という明確な基準がないのです。
パパ見知りが起こる原因
では、なぜ「ママ見知り」はなく、パパだけに対して人見知りが起こるのでしょうか?パパ見知りの原因について見ていきましょう。
パパ見知りの原因は、赤ちゃんが成長して、ママ以外の人を区別することができるようになったからです。
赤ちゃんは生まれる前からママのお腹の中で長い時間を過ごし、産後もママにお世話をされる機会が多く、赤ちゃんはママに対して安心感を抱きます。
ママとの信頼関係がしっかりとでき、ママを母親として認識できるようになったという認知能力の発達から起こります。
安心してください、パパに不安や恐怖を抱いてパパ見知りをしているのが理由ではありません。
単に、パパと一緒に過ごす時間の長いママの方が安心でき、常に一緒にいてほしい存在として赤ちゃんが認識しているため、パパ見知りが起きるのです。
パパ見知りの対処方法を紹介

パパ見知りの状態になると、パパもどうしたらいいのか分からず、育児から遠のいてしまうパパもいるかもしれません。
しかし、パパ見知りになった時の上手な対処方法を知ると、パパ見知りも早く終わり、赤ちゃんにニコニコしてもらえるようになるかもしれません。
では、パパ見知りの対処方法について見ていきたいと思います。
パパが赤ちゃんと接する時間を増やす
パパ見知りの対処法の第1歩は、赤ちゃんと接する機会を増やすことです。
まずは、ママも交えて親子一緒に出かけたり、夜寝る前に赤ちゃんのお気に入りの絵本を読んであげたりして、赤ちゃんと触れ合う時間を増やすとよいでしょう。
パパが近くにいると赤ちゃんが人見知りの反応を強く示すようであれば、無理はせずに、わからないように遠くから様子を見守ることから始めましょう。
仕事で帰りが遅いパパや、赤ちゃんと一緒に暮らしていない単身赴任中のパパは、赤ちゃんと接する時間が短く顔を覚えてもらいにくいため、赤ちゃんにはパパが知らない人の対象になってしまいます。
パパが単身赴任中などで赤ちゃんと触れ合う機会を作るのが難しい場合は、赤ちゃんの目のつくようなところにパパの写真を飾ったり、パパと遊んだ時の動画を観たり、テレビ電話などを利用してパパの顔を認識してもらったりして、赤ちゃんがパパに慣れるための対策をとりましょう。
赤ちゃんとの関わりを避けない
パパ見知りになると、パパもどう接したら良いのか分からなくなり、ショックから赤ちゃんとの関わりを避けるような生活をしてしまうパパもいます。
しかし、赤ちゃんを避けていると余計に赤ちゃんに認識してもらえず、パパ見知りも長引いてしまいます。
パパ見知りをしている時は、パパのお世話を嫌がるかもしれませんが、夫婦で協力しながら諦めずにできることからやってみましょう。
そして、赤ちゃんは敏感なのでイライラせずになるべく笑顔で話しかけるようにしましょう。
ママと仲良くする
パパ見知りは、赤ちゃんの不安な気持ちが原因です。
赤ちゃんの不安を和らげるには、パパもママと同じ赤ちゃんの親であることが分かってもらえるよう、赤ちゃんの大好きなママと仲良くしている姿を見せることです。
赤ちゃんが、ママとパパが仲良くしている様子を見続ければ「この人は、安心できる人」と認識します。
パパならではの遊び方で遊ぶ
パパにしかできないダイナミックな遊び「肩車」や「高い高い」「お馬さんごっこ」などは、赤ちゃんの大好きな遊びです。
赤ちゃんの機嫌のいい時に、こういった遊びを選んで取り入れるようにし「パパといると楽しい」と思ってもらうように努めましょう。
パパ見知りをしている赤ちゃんにしてはNGな行動
パパ見知りで泣いている赤ちゃんに対して、イライラしたり、大声で怒鳴ったり、嫌がっているのに無理強いをしたりすることは、赤ちゃんの「恐怖心」をあおってしまいます。
ゆったりした気持ちで接してあげましょう。
「赤ちゃんに拒否されているから」との理由から赤ちゃんとの関わりをやめてしまうと、赤ちゃんとの距離も縮みません。
たとえ泣かれてしまっても、ミルクをあげたりオムツを変えてあげたりしながら赤ちゃんとの関わりを続けることが大切です。
まとめ
パパ見知りが起こる時期や原因や対処方法についてみてきました。
いかがだったでしょうか。
赤ちゃんがパパ見知りをして、多くのパパが「嫌われている」とショックを受けるでしょう。
しかし、赤ちゃんはパパが嫌いだからパパ見知りをするのではなく、パパ見知りは赤ちゃんにとって成長の証で一時的なものなのです。
焦らずに諦めることなく、なるべくゆったりとした気持ちで赤ちゃんとの時間を楽しむようにしましょう。
そうすることで、赤ちゃんもきっと笑顔をパパに見せてくれるようになるでしょう。
この記事を書いた
サポーターママ
 おーちゃんママ
3女のママ
おーちゃんママ
3女のママ
3姉妹のママです。現在は、隙間時間を見つけてライターの仕事をしています。
第1子は、初めての育児で育児書通りのガチガチ育児を経験、第2子は、2歳差育児に奮闘して頑張りすぎ育児を経験、第3子は、完全ゆるゆる育児を実践中です。
私自身も、これまで多くの世のママさんたちの言葉を道しるべに育児をしてきました。
今度は、少しでも頑張っているママさんたちの力になれれば良いな。という思いで発信していきたいと思っています。
この記事が気に入ったらシェア
歯科医師 ゆう歯科クリニック
監修
伊藤裕章先生 監修