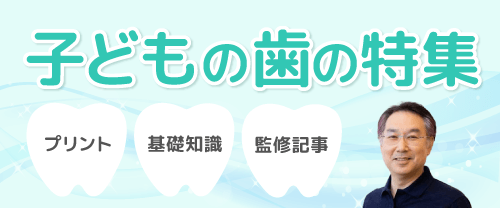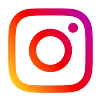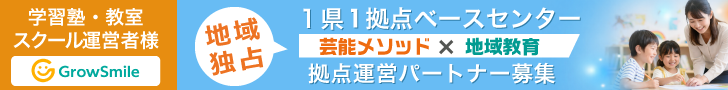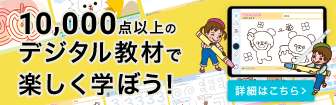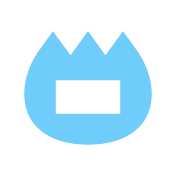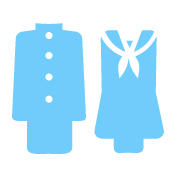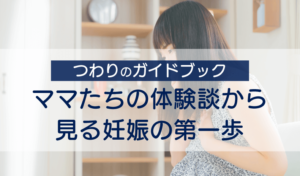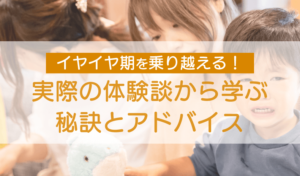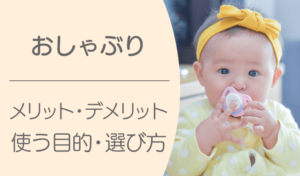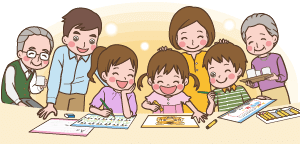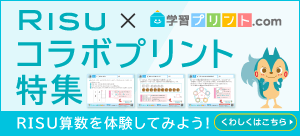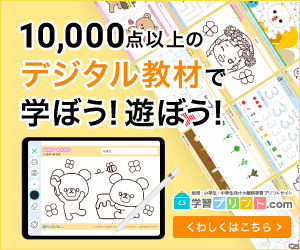赤ちゃんが歩き始めるタイミングは?練習は必要?時期の目安や歩き始めの注意点も

赤ちゃんの成長はとても早いものです。
寝返りをして、ハイハイをして、日々の成長の速さに私たち親がビックリしてしまいます。
この前まで出来なかった事が出来るようになって、我が子の成長をとても嬉しく感じますよね。
そろそろ歩き始めるころかと楽しみにしているパパやママも多いと思います。
まだかまだかと待ち遠しくも感じているでしょう。
私も子どもが歩く日を心待ちにしていました。
初めて歩いた時には家族みんなで大喜びしたのを覚えています。
つい最近まで一日の大半を寝ていた小さな赤ちゃんが、自分の足で一歩進む瞬間は感動的なものです。
赤ちゃんが足を広げてヨチヨチ歩く可愛い姿を早く見たいですよね。
この記事では赤ちゃんの歩き始めについて詳しく説明していきます。
うちの子は少し歩くのが遅いのではないかと心配している方にも読んでいただけたらと思います。
また、歩行練習や赤ちゃんが歩き始める際に、私たちが気を付ける事も併せて書いていきます。
赤ちゃんが歩く時に安心できる環境をしっかり整えておく為に、是非参考にしてみてください。
赤ちゃんが歩き始めるタイミングは?

赤ちゃんが歩き始めるのは、平均するとだいたい1歳前後ぐらいです。
赤ちゃんの成長にともない、体重が少しずつ増加し、足や他の部分でも筋肉が発達する事で、全身でバランスをとりながら歩けるようになっていきます。
また、パラシュート反射というものがあります。
これは、生後6ヶ月ごろから1歳ごろにあらわれる特徴の一つで、前かがみになった際に、手を前に出して体を支えようとする能力の事です。
パラシュート反射は生後9ヶ月から10ヶ月ごろの乳幼児健康診査でも確認をします。
このパラシュート反射は成長の過程で身につくものであり、合わせて、赤ちゃんが歩けるようになるための重要な機能の一つとされています。
歩き始めは転んでしまう回数も多いので、手を前に出して体を支える動きがないと頭を打ってしまいます。
人は、筋力、反射の発達、バランス感覚など、複数の成長を経て歩く事が出来るようになるのです。
その成長速度は赤ちゃんの発育によって大きく異なるものです。
ですので、早く歩けるようになる事がいいわけではありません。
1歳半過ぎまでハイハイしている子どももいれば、2歳間近で歩き始める子どももいます。
また、歩き始めるまでの期間が長い場合は、赤ちゃん自身の性格が影響しているかもしれません。
歩くという行動には赤ちゃんのやる気もとても影響しています。
体は成長していても赤ちゃん自身が歩きたいと思う気持ちが大切です。
または、慎重な性格で1歩目が出るのに時間がかかる赤ちゃんもいます。
赤ちゃんが歩きたいと思う環境作りをしてあげるのもいいかもしれません。
この他にも歩く時期が遅れる理由にシャフリングベビーの可能性があります。
ハイハイや立つ事を嫌がり、座ったまま前に進もうとする赤ちゃんの事をそう呼んでいます。
シャフリングベビーの場合も、2歳になるころまでには歩く赤ちゃんが多いです。
その後、成長も他の赤ちゃんと変わりない事が多いので、赤ちゃんの個性のひとつと言えます。
このように1歳前後というのはあくまで目安となるものです。
歩き始めるタイミングもまた個性であり、赤ちゃんの体や心の準備が整うのを楽しみに待ちましょう。
歩き始めるのが遅いからといって、運動の機能が発達していないということでないため、あまり神経質にならなくても大丈夫です。
ですが、我が子が歩くのを楽しみにしているからこそ、まだ歩かないのかと心配になる事もありますよね。
心配な時は、様子をみて、検診の際に小児科に相談するとパパとママも安心するのではないでしょうか。
また、もし歩かない事の他にも成長速度がちょっと遅く感じたり、笑う事が少ない等、気になる場合も病院で相談してみましょう。
歩行練習は必要?

赤ちゃんが歩く為の練習は特に必要ないとされています。
歩く為に必要な筋力やバランス感覚は、赤ちゃん自身のペースで身につけていきます。
ですが、その手助けとして歩きやすい環境作りをしてみてはいかがでしょうか。
赤ちゃんの多くは生後10ヶ月ごろまでにつかまり立ちをします。
つかまり立ちは足の筋肉の力がついてきた証であり、歩くまでに必要な段階です。
その後、つたい歩き、ひとり立ちという流れになりますが、そこからなかなかひとり歩きをしない場合があります。
身近につかまって立ったりできる場所が多いと、歩こうとする機会が減ってしまうのです。
つかまる場所を減らす事、パパとママが手を離し「おいで」と声かけをする事、少しずつ歩きやすい環境にしていきましょう。
また、おもちゃを使うなどして赤ちゃんの好奇心を伸ばしてあげるのもオススメです。
歩行練習に向いているおもちゃとして歩行器や手押し車があります。
以前は赤ちゃんの歩行訓練のために、よく歩行器を使っていたといわれますが、どちらも遊びながら歩く事への興味を持つ手助けになります。
選ぶ際は子どもによって興味を示すものが違うので、実際に店頭で子どもと見ながら選ぶとよいでしょう。
ですが、おもちゃを活用しても必ず歩けるまでテンポよく進むわけではありません。
我が家の子ども達は同じ手押し車を使って遊ばせていましたが、それぞれ歩き始める時期は違いました。
その中でも末っ子は、手押し車は大好きでしたが、なかなかひとり歩きに進みませんでした。
最初の一歩を出すのが難しく、慎重派の赤ちゃんだったようです。
それでも、声かけをしたり一緒に手押し車で遊んでいるうちにあっという間に上達していきました。
パパとママの中には、子どもが歩かない事で不安を抱えている方も多いかと思います。
そんな時は焦らず、身体がしっかり成長し、子ども自身に歩きたいという欲求が出てくるまで温かく見守りましょう。
そして、歩く意欲がわくような遊びを生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
子どもが一人で少しずつ数歩を歩き始めたら、次のステップに向け、赤ちゃん用のファーストシューズを準備して、公園などに出掛け、外で歩く練習をしてみましょう。
ファーストシューズを出産のお祝いでもらった方もいるかもしれませんね。
ファーストシューズを購入する際、靴のサイズは3~4ヶ月先の足のサイズを目安に、少し大きいものを選ぶようにします。
靴の形は、つま先の幅が広く、靴の中で指が自由に動くようなタイプの靴を選ぶと、転倒防止につながります。
また、O脚などの足の変形を防止するため、靴のかかとまわりがしっかりと安定しているものを選ぶと、かかとの骨の成長を促す助けになります。
もし靴がお子さんにフィットしているかどうか分からなかったら、お店でシューフィッターなどの専門家に相談をして、靴の選び方を教えてもらうとよいでしょう。
公園に行くときは、服も動きやすいものを選んであげるといいですよ。
歩き始めの注意点

【家の中の危険な箇所一覧】
| 危険箇所 | 注意する内容 |
|---|---|
| 家具やテーブルの角 | 角に頭をぶつけてしまう可能性があります。 クッション材などを取り付け、ケガを未然に防ぎましょう。 |
| 玄関 | 玄関の段差から転落したり、玄関ドアを自分で開けて外に出てしまう恐れがあります。 子どもが玄関に近づかないように注意を払うとともに、玄関は常に施錠をするようにしましょう。 |
| ベランダ | ベランダから転落する可能性があるため、窓には補助の鍵をつけるなどして、あらかじめ、子どもがベランダに近づかないような対策をしておきましょう。 |
| 階段 | 子どもが階段から転落する恐れがあるため、ベビーゲートなどを取り付け、子どもが階段を上らないように注意しましょう。 |
| 浴槽 | 子どもが浴槽に転落すると、少しの水でも溺れる可能性があります。 浴槽の水はためておかないようにし、子どもが風呂場に近づかないように鍵をかけるなどの工夫をしましょう。 |
| コンセント | よだれのついた指で触ると感電する恐れがあります。 また、コンセントにつながった電気製品などが高い位置にあると、子どもがコンセントを引っ張って上から落下する可能性があります。 使っていないコンセントがあればカバーをつけ、電気製品はコンセントから抜いて子どもの手の届かない場所に置き、落下を防止しましょう。 |
気を付けないといけない事は沢山ありますが、一番重要なのは子どもから目を離さない事です。
家の中はもちろんですが、外出先でも注意が必要です。
今までは抱っこ紐やベビーカーに乗せていたので、目の届く範囲でよかったはずです。
ですが、歩き始めると自分で歩きたがるため、抱っこを嫌がったりします。
子どもは大人の想像もしないような場所に行ったり、隠れたりするので迷子になりやすいです。
事故や事件を未然に防ぐ為にも、子どもから目を離さない事を徹底し、手を繋いでお出掛けするようにしましょう。
また、周りに危ない物がないか、ぶつかりそうな場所はないか、たくさんの場所をよく注意する必要もあります。
次男が歩き始めた時になりますが、転んだ際に長男が使っている子供用の椅子で口を強打した事がありました。
その時は口から大量に出血してしまい、病院に駆けこんだのを今でも鮮明に思い出します。
当時は長男が赤ちゃんの時よりものが増えていました。
転んだりぶつかる可能性が高かったのに対し、私の注意不足が原因です。
すでに家具やテーブルの角をガードしたり、ぶつかりそうなものは手の届く範囲に置かないようにしているご家庭も多いと思います。
しかし、歩き始めると気を付けなければならない範囲が広がってきます。
ドアノブに手が届くようになると、他の部屋にも気を配らなければなりません。
また、玄関に段差がある場合は落下防止、玄関のドアの施錠も必須になります。
ベランダがあるご家庭は、子どもの手が届かない場所に補助の鍵を取り付けたり、窓に近づかないようにベビーゲートを置くようにしましょう。
家の中に階段がある場合は、子どもが一人で階段を上って倒れたりしないよう、ベビーゲートをつけるなどの対策も必要です。
他にも水回りには気を付けてください。
少し目を離すと大きな事故につながる可能性があります。
浴槽には少しでも水をためておかない事が大事です。
可能ならお風呂場や脱衣所には子どもが入らないように鍵を閉めておくといいでしょう。
子どもは好奇心が旺盛ですし、何が危ないのかまだ判断できません。
歩けるようになって行動範囲が広がってくると、いつの間にか移動している事もよくあります。
目を離さない事はもちろんですが、念のために少しでも危険がある場所には、何か問題が起こる前に対策しておくようにしましょう。
まとめ
赤ちゃんが歩き始める時期は赤ちゃんによって異なります。
まだ歩かないと心配しすぎず、可愛い我が子が歩く姿を楽しみに待ちましょう。
必死にバランスを取りながら一歩ずつパパやママの元に歩いて来る日が楽しみですね。
また、歩き始めると赤ちゃんの行動範囲が広がります。
その分好奇心も旺盛になり、いろいろな事に興味を持ち始めます。
ヒヤヒヤする場面も増えてくるはずです。
子ども達が怪我をしないように私たち親が目を離さず、近くで成長を見守っていきましょう。
この記事を書いた
サポーターママ
 なゆこママ
2男1女のママ
なゆこママ
2男1女のママ
ママっ子の長男、マイペース次男、パパ大好き末っ子長女の3人子育てに奮闘中のママです。
最初は育児書の通りしないといけないと頑張り過ぎていました。
今は程よく手を抜きながら子どもと一緒に毎日笑顔で過ごせるのが目標です。
料理、お菓子作りが好きで、節約しながらも子ども達が喜ぶご飯を作ることを常に意識しています。
まだまだ未熟なママですが、我が家の育児方針や子ども達の成長過程が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
また、いろいろな方と接する事で自分自身も成長していきたいと思います。
この記事が気に入ったらシェア
歯科医師 ゆう歯科クリニック
監修
伊藤裕章先生 監修