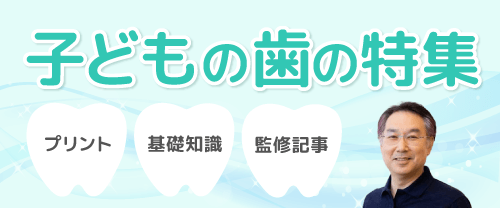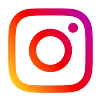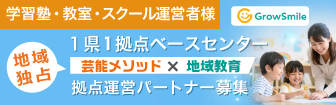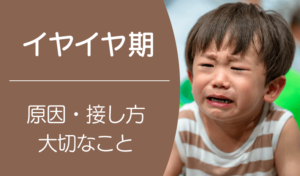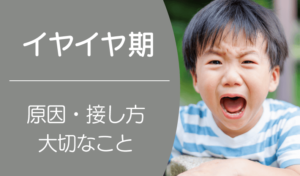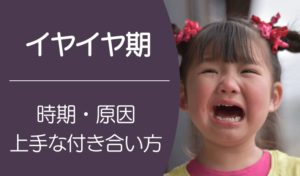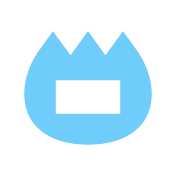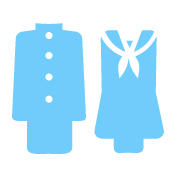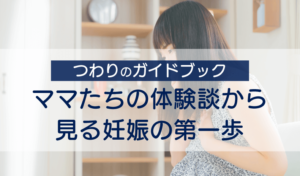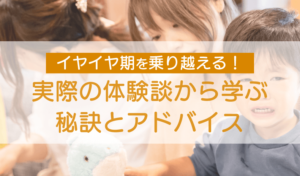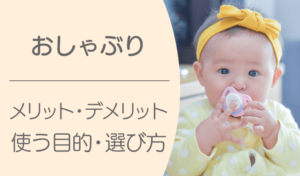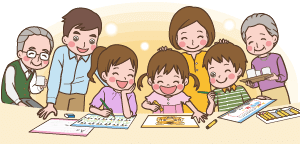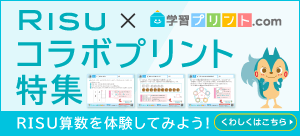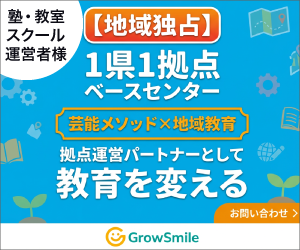イヤイヤ期(2歳児)はいつからいつまで?原因と上手な付き合い方をご紹介
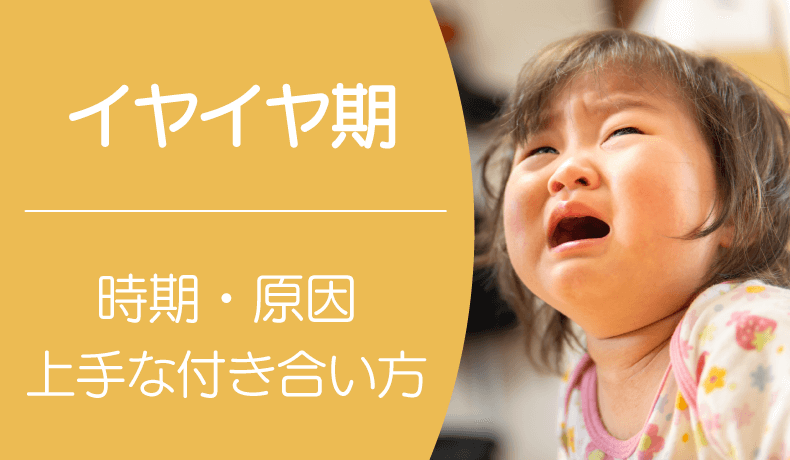
「イヤイヤ期」は子どもの成長の証であり、子どもにとってとても大事な時期です。
イヤイヤ期を通して子ども達は大きく成長していきます。
ですが、時間や場所に関係なく、子どもに「イヤ」と言われると困ってしまう事も多いですよね。
外出先で床に寝ころんでイヤイヤと言われたり、おもちゃ屋さんでおもちゃが欲しいと駄々をこねられたりすると、周りの目も気になって私たち大人も心理的にストレスを感じてしまいます。
また、子どもにイヤイヤが出るなどして感情的になられたりするとスムーズに家事や育児が進まない事も増えていきます。
大切な期間と分かっていても、イヤイヤ期に直面すると困惑してしまう事もありますよね。
子育てをしていると、この子どものイヤイヤ期を経験する方はたくさんいらっしゃるでしょう。
いつ始まるんだろう、いつまで続くんだろう、どう対応したらいいんだろう、とイライラを感じることで悩む方も多くいるのではないでしょうか。
この記事では、イヤイヤ期とはどういうものなのか、いつ頃始まりいつ頃おわるのか、我が家の実体験とあわせて説明していきます。
また、イヤイヤ期に突入した子ども達とうまく付き合う付き合い方もご紹介していきたいと思います。
イヤイヤ期について理解する事で、子どもの気持ちを知って、私たちも子ども達と一緒にこの期間を乗り越えていきましょう。
イヤイヤ期とは?

イヤイヤ期は子どもが何に対しても「イヤ」と言ったり、何でも自分でやると自己主張したりするのが特徴で、この間の期間が「イヤイヤ期」と呼ばれる期間です。
私たち親からすると、なぜイヤイヤばかり言うのかと、頭を悩ませる時期でもあります。
このご飯は食べたくない、着替えたくない、お風呂に入りたくない、毎日「イヤ」のオンパレードで大人も疲れてしまいます。
ひどい時は、泣きすぎて最終的には自分は何がイヤなのか分からないという場面もよくあります。
我が家の子ども達は「公園から帰りたくない」とよく無理を言って駄々をこねていました。
「家まで競争しよう」と遊び感覚で提案しても何も聞いてくれません。
時間ギリギリまで待ったり、声かけをしたりしますが帰ってくれる事はありませんでした。
抱っこして強制的に帰る日も多かったです。
そんな時は、ママよりパパがいいと言われた事もよくあります。
また、イヤイヤ期の頃は一度泣き始めると、周りの声が聞こえない程泣いて嗚咽をもらしていました。
何がイヤなのか、どうしたいのか聞いても泣くばかりです。
何も答えないのではなく、どう答えたらいいのか分からなかったのでしょう。
子どもは成長の過程で自己主張が強くなっていきますが、まだ感情を表現する事が難しいのが現状です。
「やりたかったのに」「そうじゃないのに」「何で分かってくれないのか」を大人のように上手く伝えきれません。子ども達は自分の思い通りにいかない気持ちを「イヤ」という言葉で精一杯伝えているのです。
そんな子ども達も徐々に自分の感情を自分の言葉にして相手に伝える事が出来るようになります。
この期間は何でこんなにワガママなんだろうと思うことも少なくないと思います。
ですが、子どもが成長している証なのです。
この前生まれてきてくれたばかりだと思っていたのに、成長の早さにビックリしてしまいますよね。
ですから、喜ばしい事だと分かってはいるんです。
イヤイヤ期も必要な期間だと分かっています。
しかし、何を言っても「イヤ」と言われると、心が折れそうになってしまう事もあります。
「ママイヤ!」と言われた時は私が泣きたくなる時もありました。
ただし、子どもが言う「イヤ」は必ずしも直訳の「イヤ」という訳ではありません。
どう言ったらいいのか分からないから「イヤ」と言ってしまいます。
ママやパパに分かってほしいという気持ちがこもっているんです。
そう思うと少し心穏やかに接する事が出来るような気がしませんか。
イヤイヤ期はいつからいつまで?

イヤイヤ期は早い子なら生後6ヶ月から1歳前後に始まり、4歳頃には落ち着く事が多いようです。
また、この時期はママじゃないと嫌だと言ってパパを拒否する「パパイヤ期」が訪れる子もいます。
年齢別イヤイヤ期の特徴と対処法の一覧
| 子どもの年齢 | イヤイヤの特徴と対処法 |
|---|---|
| 0歳 (生後6ヶ月ごろ) | 自己主張が始まると、寝返りがうまくできなかったり、離乳食の味が気に入らないなどの理由で泣き出したりします。 赤ちゃんの機嫌が落ち着くまで優しく見守るなどしてあげましょう。 |
| 1歳 | 歩き始めると興味のあることがどんどんと増えてきます。自分の思い通りにいかない、やりたいことがうまくできないなどの理由でイヤイヤが始まります。 親が子どもの気持ちに共感したり、他のことに興味を移らせるなどして対処してみましょう。 |
| 2歳 | 「魔の2歳児」とも呼ばれ、本格的なイヤイヤ期に突入します。1歳の時よりもさらに自己主張が強くなり、ワガママを言うようになるでしょう。他のことに興味を移させるのも一苦労するようになります。 その場合は、子どもが気が済むまでやらせてあげたり、子どもを否定せずに、抱きしめて気持ちを落ち着かせるようにしましょう。子どもの気持ちに共感してあげることが大切です。 |
| 3歳から4歳 | 他のお友達と遊ぶ機会がどんどんと増えてきます。そのためお友達との意見の違いやおもちゃの取り合いなどで、気持ちが爆発してかんしゃくを起こしやすくなります。 気持ちをうまく伝えられず衝突が起きたりするため、大人がその気持ちを受け止め、抱きしめてスキンシップをとったり、言葉での共感をしてあげましょう。 |
1歳前後に自我が芽生えてくる事によって自己主張する子どもが増えていきます。
イヤイヤ期が始まると2歳ごろにはピークを迎えます。
よく「魔の2歳児」と耳にする事も多いのではないでしょうか。
この2歳の頃が1番大変だったとよく聞きます。
ですが、自我が芽生え始める時期も、イヤイヤ期が落ち着いてくる時期も個人差があります。
我が家の子ども達に関してですが、長男は私が次男を妊娠中の2歳後半にイヤイヤ期が始まりました。
3歳になってすぐにピークを迎え、3歳後半には落ち着いた様子でした。
次男も同じくらいだと想像していたんですが、次男は3歳の半ばから始まりました。
その後すぐにピークが来たようで、4歳目前の現在も思い通りにいかずいろいろなことを拒否して、毎日泣いたり怒ったりしています。
兄弟でも上の子と下の子で始まる時期が違う状況でした。
特に長男の場合は、ママの妊娠出産を感じとった事がイヤイヤ期に影響したようです。
弟が出来て嬉しい反面、寂しい気持ちをどうしても上手く伝えきれず親の気をひく行動をしていました。
個人差の他にも、このように子どもの周りの環境等たくさんの要因があります。
イヤイヤ期がいつからいつまでと断定したり、他の子と比較するのは難しいでしょう。
また、パパやママが「イヤイヤ期かもしれない」と認識する程度も人それぞれ違います。
子どもが「イヤ」とよく言うようになっても、それをイヤイヤ期程ではないと思う場合もあります。
うちの子にはイヤイヤ期はなかったと思う方もいます。
イヤイヤ期は1歳前後から4歳頃までが多いですが、時期も度合も個人差があります。
うちの子もそろそろイヤイヤ期が始まるかもしれないと思うくらいの気持ちを持って乗り切るといいかもしれません。
イヤイヤ期の原因と上手な付き合い方

先ほど子どもの自我が芽生え始める事でイヤイヤ期を迎えると言いました。
これは年齢が大きくなる間に、脳の未発達部分が成長していく過程で起こるとも言われています。
自我が強くなって自立していくのに対し、それをコントロールする脳がまだ未発達のため起こります。
この脳が成長する事でイヤイヤ期が落ち着いていきます。
イヤイヤ期にも理由があり、大事な時期なのです。
ではこのイヤイヤ期をどう対処したらいいのか対処法をご紹介したいと思います。
まずは嫌がる子どもの気持ちに共感して接してください。
最初に「そうだよね、イヤだったね」と話を聞いて共感してあげる事が大事です。
子どもが危険を伴うようなことをしている場合など、時には「それはダメだよ」と注意するなど、叱りの場面もあるかもしれませんが、そうじゃない場合は、なるべく「ダメ」と言わずに共感してあげることで、自分の事をちゃんと分かってくれたんだと気持ちが落ち着いていきます。
これは私も子どもに対して実践してきました。
子どもの気持ちや要求をしっかり受け止めてあげると子どもの不安も消え、自己肯定感が高まります。
自己肯定感が高まると将来的にも自信を持って自分の意見を言えるようになります。
また、イヤイヤ期は子どもが「自分でやりたい」が増える時期です。
忙しい朝や仕事で時間がない時は先回りにして、つい親が全部やってしまいがちだと思います。
余裕がある時は、ひとつだけでも実際に子どもにやらせてみましょう。
自分で出来たという達成感は子どもにとってとても大きなものです。
朝、服を着る時に自分で選びたいと泣いてしまう事もよくあります。そういう時は、洋服を2種類出してどちらがいいか子どもに決めてもらいます。
選択を自分でする事で子どもの欲求も満たされる場合が多いです。
我が家の次男は朝ご飯の食事の時間にイヤイヤが発動します。
朝ご飯は食べてもらいたいけど複数作ったりするのは難しいため、すぐ出せるシリアル等を別に準備するようになりました。
「今日はどっちにする?」と確認して、毎朝自分で選んでもらっています。
子どもの気持ちに共感する、子ども自身にやらせてみるなどの対策をとって、子どもの成長を促してあげましょう。
公共の場では、子どもの気持ちを変えられるようなぬりえや絵本などを持って行くようにし、子どもの意識がそちらに向けられるような対策を取るのも効果があります。
どうしてもイヤイヤ期の対処が難しい時は、公共のサービスや、地域で育児の悩みや質問を受けている場所を利用して相談してみるのもいいですね。
まとめ
最後になりますが、これもとても大事な事です。
子どものイヤイヤは甘えたい、自分を見てほしい、を必死に伝えています。
子どもに共感すると同時に抱きしめてあげてください。
自分は愛されているんだと安心し、それが自信にもつながります。
毎日繰り返す「イヤ」の連鎖に私たち親は悩んでしまうでしょう。
イヤイヤ期の度合いも期間もそれぞれ違い、親にとっても悩みが異なります。
ですが、イヤイヤ期は必ず終わりがあります。
いつまで続くんだろうと心配にもなりますが、いつの間にか落ち着いていくものです。
あんな時期もあったと思い返す時が来るのです。
魔の2歳児と言うけど、そんなに酷くなかった気がすると思うかもしれません。
これからイヤイヤ期を迎える方も、イヤイヤに悩んでいる方も、一緒に上手く付き合っていきましょう。
この記事を書いた
サポーターママ
 なゆこママ
2男1女のママ
なゆこママ
2男1女のママ
ママっ子の長男、マイペース次男、パパ大好き末っ子長女の3人子育てに奮闘中のママです。
最初は育児書の通りしないといけないと頑張り過ぎていました。
今は程よく手を抜きながら子どもと一緒に毎日笑顔で過ごせるのが目標です。
料理、お菓子作りが好きで、節約しながらも子ども達が喜ぶご飯を作ることを常に意識しています。
まだまだ未熟なママですが、我が家の育児方針や子ども達の成長過程が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
また、いろいろな方と接する事で自分自身も成長していきたいと思います。
この記事が気に入ったらシェア
歯科医師 ゆう歯科クリニック
監修
伊藤裕章先生 監修