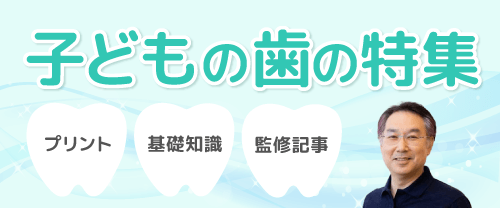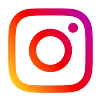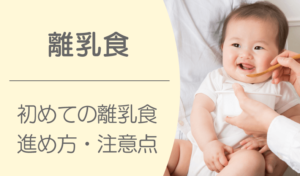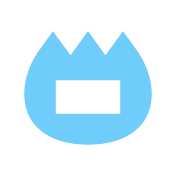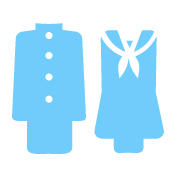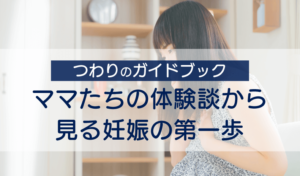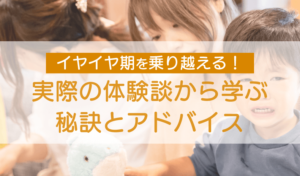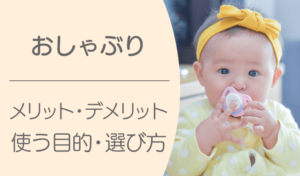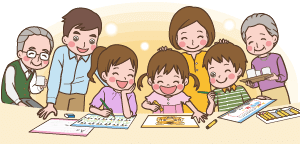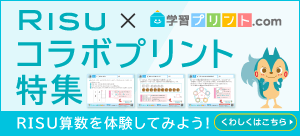赤ちゃんのママ必見!離乳食の進め方、注意点、よくある悩み事

「離乳食」という言葉は知っていても何から始めたらよいのか、どのように進めていくのかご存知ですか。
生後5、6ヶ月頃を過ぎると母乳やミルクだけではだんだんと栄養が足りなくなってきます。
その栄養を補うため、母乳やミルク以外の食べ物を食べられるように練習するため、食べることの楽しさを知るために必要なのが「離乳食」です。
赤ちゃんの身体機能はまだまだ未発達なので、離乳食では赤ちゃんの成長に合わせて食材を調理し、食べられる量や種類を増やしていきます。
離乳食の進め方や注意点、よくある悩み事についてご紹介していきます。
目次
赤ちゃんのママ必見!離乳食の進め方

離乳食を始める目安は生後5、6ヶ月頃です。
赤ちゃんによって発育や身体の大きさも様々です。
生後5、6ヶ月頃になると赤ちゃん自身が離乳食を始める準備が出来ているのか様子をみてみましょう。
離乳食開始の目安
- 生後5、6ヶ月になっている
- 赤ちゃんの首がすわっている
- 支えてあげるとお座りができる
- よだれの量が増えてきた
- 生活のリズムが整い、授乳の時間が一定になってきた
- 赤ちゃんが食べ物に興味をしめしている
- ママの心の準備が出来ている
- 赤ちゃんの体調が良い
などが当てはまっていたら離乳食を進めていきましょう。
すべてが当てはまらなくても大丈夫です。
離乳食は教科書通りには進みません。
赤ちゃんによって1人1人違うので周りの子と比べて進みがおそくても焦る必要はありません。
ママも頑張りすぎず、心の余裕をもって進めていきましょう。
進め方のポイント
- 食材の種類や固さ、形を赤ちゃんの月齢や発達に合わせる
- 食材は加熱する(加熱することで殺菌効果があります)
- 調味料は使わず、だしで調味する(生後9ヶ月頃〜風味づけとして使用することができます)
- 初めての食材は病院の休診日を避け、午前中に与える(アレルギーの心配があるため)
- 初めての食材は1日1種類1さじずつ与える
- 初めての食材を食べたとき後は便や発疹など赤ちゃんの身体を観察する
- 赤ちゃんの体調が悪いときには無理に進めない
月齢ごとの進め方やポイント
離乳食初期:生後5、6ヶ月頃
離乳食開始の目安を参考に離乳食を始めましょう。
食べ物を食べる練習に慣れていく時期です。
- 離乳食の回数 : 1日1回、離乳食を開始して1ヶ月たった頃から1日2回にしていきます。
- 授乳 : ミルクは月齢に合わせた回数と量で、母乳は欲しがるだけ与えましょう。
離乳食前にお腹がいっぱいになってしまうと食べなくなることもあります。
午前中の授乳の時間を離乳食に置き換え、離乳食を食べ終わった後に欲しがるだけミルクや母乳を与えるようにしましょう。
- 食べ物の固さ : 食材はトロトロに。ヨーグルトのような状態が目安です。
- 食べ物の形 : おかゆ 10倍がゆ、野菜や豆腐、魚は裏ごししてペースト状にしましょう。
離乳食中期:生後7、8ヶ月
だんだんと離乳食のリズムがついてきます。
離乳食にも慣れてきて食べる量が増えてくる時期です。
トロトロの状態のものから徐々に固さや形をつけていくため、食べ物をもぐもぐして飲み込む練習期間です。
- 離乳食の回数 : 1日2回
- 授乳 : ミルクは月齢に合わせた回数と量で、母乳は欲しがるだけ与えましょう。
- 食べ物の固さ : 舌でつぶせる固さ。豆腐やプリンのような固さが目安です。
- 食べ物の形 : おかゆ 7〜5倍がゆ、野菜・魚・肉はペースト徐々から徐々にみじん切りにしていきます。
離乳食後期:生後9〜11ヶ月
やわらかい固さのものをもぐもぐ食べられるようになってきます。
離乳食の回数も3回になり、手づかみ食べの楽しさを味わうじきです。
- 離乳食の回数 : 1日3回
- 授乳 : ミルクは月齢に合わせた回数と量で、母乳は欲しがるだけ与えましょう。
食べる回数や量が増えるとだんだんと授乳の量や回数が減ってきます。
赤ちゃんの様子に合わせてあげましょう。
- 食べ物の固さ : 歯茎でつぶせる固さ。熟したバナナくらいの固さが目安です。
- 食物の形 : おかゆ 5倍がゆ〜軟飯、野菜・魚・肉もみじん切りから徐々に大きく5〜7mmくらいにしていきます。
手づかみ食べ
生後9ヶ月を過ぎると、赤ちゃんが自分の手や指を使って食べ物を触ろうとしたり、口に入れようとしたりするようになります。
赤ちゃんの発達に合わせて手づかみ食べを始めてみましょう。
しかし、最初から上手く手づかみ食べが出来る赤ちゃんはあまりいません。
食べ物をこねたり、つかんでは落としてみたり、大人にとっては食べ物で遊んでいるように見える行動も多いでしょう。
しかし、赤ちゃんにとっては食べ物を自分の手で確認して学んでいる大切な時間です。
汚れても大丈夫な環境を用意して、赤ちゃんに思う存分手づかみ食べを楽しんでもらいましょう。
離乳食完了期:生後12~18ヶ月
離乳食の完了期とは栄養のほとんどを離乳食からとるようになり、形のある食べ物を噛みつぶして食べられるようになったということです。
手づかみやスプーンなどで食べる喜びをあじわいましょう。
- 離乳食の回数 : 1日3回
- 間食 : 1日1〜2回
- 授乳 : ミルクや母乳の量も徐々に減っていきます。
- 食べ物の固さ : 歯茎でつぶせる固さ。指でつぶせるバナナくらいの固さが目安です。
- 食べ物の形 : ご飯 軟飯〜普通飯、野菜・魚・肉 徐々に大きく1cmくらいの大きさにしていきます。
赤ちゃんの間食「おやつ」
1歳を過ぎると赤ちゃんは栄養のほとんどを離乳食からとるようになります。
そして成長に必要なエネルギーや栄養素もさらに増えます。
しかし、赤ちゃんの胃袋は小さく消化吸収能力もまだまだ未熟です。
そのため1日3回の食事だけでは栄養が不足してしまうことがあるので、その栄養を補うために「間食」を与えましょう。
赤ちゃんのおやつは栄養とエネルギー補給が目的なので、おにぎりやいも類、果物などがおすすめです。
赤ちゃんのママ必見!離乳食の注意点

離乳食での注意点をご紹介していきます。
赤ちゃんの月齢や成長に合った食べ物かどうか
身体も心もまだまだ成長途中の赤ちゃんは、月齢や発達によって食べられる食材も様々です。
離乳食では胃や腸に負担の少ないおかゆから始めて、慣れてきたら野菜を、さらに慣れてきたら豆腐、白身魚のように徐々に種類や量を増やしていきます。
はじめて食べる食材は1日1種類にして、食材も月齢に合った食べ物かどうか確認してから与えましょう。
団子、餅、ゴマ、ナッツ類、こんにゃくなどは噛みちぎりにくく喉に詰まりやすい食材です。
離乳食期はもちろん、3歳頃までは食べないほうが安心です。
また、はちみつや黒糖はボツリヌス菌が入っていることがあるので生後1歳までは食べないようにしましょう。
食材を加熱する
離乳食は安心・安全のために加熱したものを与えましょう。
加熱は殺菌のために必要な工程です。
また加熱することで食材が柔らかくなり消化もよくなります。
生後7、8ヶ月頃まではヨーグルトや果物なども加熱してから与えます。
1歳半頃までは生で食べられる野菜も火を通すと安心です。
免疫力の弱い赤ちゃんを食中毒から守るために衛生面にも気をつけましょう。
離乳食を作るときやあげるときは必ず手洗いをして、食器や調理器具も使用したら必ず洗い、煮沸したり熱湯をかけたりして消毒しましょう。
油っこい食材に注意する
赤ちゃんにとって最も消化しにくいのが脂質です。
生後9ヶ月頃から油も使えるようになりますが、少量にして使いすぎには注意しましょう。脂質も成長にとって必要な栄養のひとつですが、脂質の多い食材やパン、加工食品などあげすぎないよう心がけましょう。
大人用のものや味の濃いものは与えない
塩分の取りすぎは赤ちゃんの身体に負担を与えます。
生後9ヶ月頃から調味料も使えるようになりますが、風味づけ程度にしましょう。
味付けなしでも食べてくれるようなら無理に使う必要はありません。
離乳食完了期でも味付けは大人の半分程度にして薄味を心がけましょう。
市販のお菓子や大人用のものは糖分・油分が多く添加物が含まれるものもあるので赤ちゃん用を与えるようにしましょう。
赤ちゃんのママ必見!離乳食のよくある悩み事

赤ちゃんによって離乳食の進み方は様々です。
離乳食でよくある悩み事についてどのように対応していけばよいのかアドバイスします。
予定日より早く生まれた赤ちゃんは生後5ヶ月から離乳食を始めてよいのか
離乳食を始める時期は目安で必ず守るべきものではありません。
予定日より早く生まれた赤ちゃんや低出生体重児の場合は出産予定日から5ヶ月を目安にするのも良いでしょう。
大切なのは赤ちゃんが離乳食を食べる準備が出来ているかどうかです。
お子様の様子をみて離乳食の準備が出来ているようなら離乳食を開始すると良いでしょう。
迷ったときはかかりつけの小児科で相談するのもおすすめです。
赤ちゃんの成長に合わせてスタートしましょう。
食べたがったら離乳食をもっとあげても良いのか
まずは、成長曲線からはみ出していないかを確認しましょう。
母乳やミルクなどで栄養がとれていれば離乳食も欲しがるだけあげて大丈夫です。
しかし、離乳食を始めたばかりの頃は注意が必要です。
消化・吸収機能が未発達なので赤ちゃんの胃に負担がかかり、アレルギーの心配もあります。
初めのうちは少しずつ増やして様子をみましょう。
離乳食初期は栄養のほとんどを母乳やミルクからとる時期です。
離乳食が増え授乳量が極端に減っている場合は、離乳食を少なめにして食後に授乳やミルクを与えるようにするのがおすすめです。
食べる量が少ない・離乳食を食べない場合
まずは成長曲線から外れていないかを確認しましょう。
赤ちゃんによって食べる量もスピードも様々です。
昨日まで食べていなくてもある日急に食べ始めることもあります。
少量でもよいので離乳食を続けてみましょう。
生まれてから母乳やミルクなど水分しか飲んだことのない赤ちゃんは、ちょっとしたつぶつぶ感やざらつきをいやがることもあります。
丁寧にすりつぶして裏ごしたり、とろみをつけたりして食べやすいよう工夫しましょう。
また、離乳食の固さや形が変わると食べなくなる赤ちゃんもいます。
そんなときには無理に進めず1段階前に戻すことも必要です。
食事の時間が長いと赤ちゃんも集中がきれてしまいます。
食べないときには無理強いはせず、時間を決めて切り上げましょう。
離乳食の前は授乳やミルクの間隔をあけたり、身体を動かす遊びをしたり赤ちゃんがお腹をすかせられる環境を作るのもおすすめです。
赤ちゃんが食事に興味をもち、楽しいと感じられるように家族で食卓を囲んだり、大人が美味しく食べる姿を見せてあげたりするのも良いです。
たくさん食べたときには赤ちゃんを褒めてあげ、焦らずゆっくりと気長に取り組んでいきましょう。
まとめ
離乳食では「昨日は食べてくれたのに今日は食べない」なんてこともよくあります。
手間をかけて作ってもなかなか食べてくれないと焦ったり悩んだりすることもあるでしょう。
「そんな日もあるよね」「今食べなくてもそのうち食べてくれる」くらいの気楽な気持ちで向き合いましょう。
悩んだときには周りに相談したり、市販のベビーフードを活用したりしながら、焦らずゆっくりと赤ちゃんのペースで楽しく進めていきましょう。
この記事を書いた
サポーターママ
 あいママ
1女のママ
あいママ
1女のママ
刺繍・裁縫などの手芸や動物など可愛いもの好きの主婦です。
自宅でベビーマッサージ講師をしています。
出産前はドラッグストアで管理栄養士として育児相談などを行ってきました。
これまで勉強してきたことや、いろいろなお母さんや赤ちゃんと触れ合ってきた経験、自身の子育てで経験してきたことを活かした記事を発信していきます。
家族みんなが笑顔になれるような、いつも頑張っている方が肩の力をぬけるような、そんなお手伝いが出来たら嬉しいです。
この記事が気に入ったらシェア
歯科医師 ゆう歯科クリニック
監修
伊藤裕章先生 監修