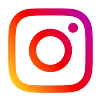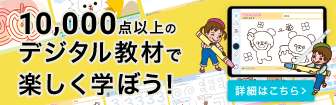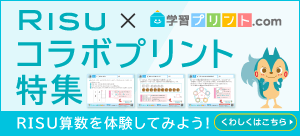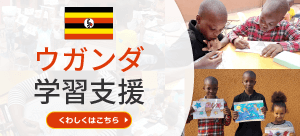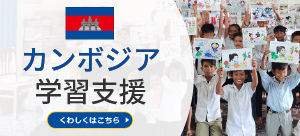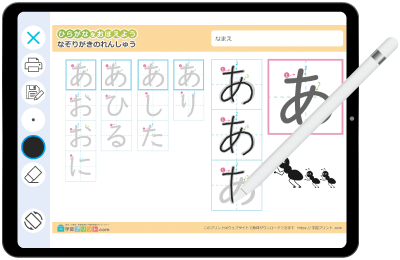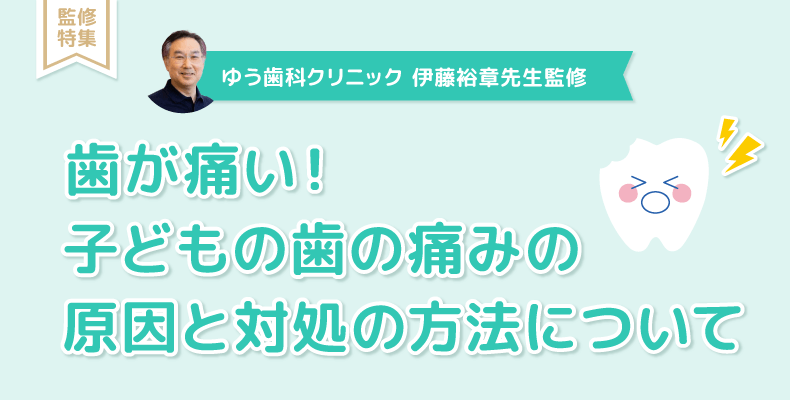
子どもから「歯が痛い」と言われると、真っ先に「むし歯になったのでは?」と心配になってしまうかもしれませんが、子どもの歯の痛みにはさまざまな原因があります。
今回のこの記事では、子どもが「歯が痛い」と訴える場合の原因を「お口の中のトラブル」と「事故やケガなどによる原因」に分けて解説し、痛みがあるときの応急処置での対処法などを見ていきます。

1986年 愛知学院大学 歯学部歯学科卒業。国家試験合格後は、実兄が開業する名古屋市中区 の「記念橋歯科」に7年間勤務し、歯牙保存の基本を学ぶ。
1994年 名古屋市西区に「ゆう歯科クリニック」を開業。その後、2018年に「医療法人 弓音会(ゆみねかい)」を設立し、医療法人としての新たなスタートを切る。
医院は「ともに生きる」を経営の理念として、人生の質に関わる「食べること」「話すこと」のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を大切にし、院長として患者さんのお口の機能の回復と健康維持に日々取り組んでいる。
歯が痛い!まずは歯の痛みの原因を探ろう
歯の痛みの原因1:お口の中のトラブル
子どもから「歯が痛い」と言われた時に、歯医者さんに相談した方がいいのか、どんな治療が必要なのかと心配になることがあるでしょう。
子どもが「歯が痛い」と言った時に、お口の中に何か問題がある場合は下記のような原因が考えられます。
むし歯
子どもの乳歯や、生え変わったばかりの幼若永久歯(ようじゃくえいきゅうし)と呼ばれる若い永久歯は、石灰化が十分に行われていないため、とても柔らかく、むし歯になりやすい特徴があります。
通常、歯はエナメル質で覆われて、その下にある象牙質が神経を守っていますが、口の中に砂糖や炭水化物などに含まれる糖が侵入することで、糖を栄養としているミュータンス菌と呼ばれる細菌が虫歯菌を出し、エナメル質に含まれるカルシウムやリンを溶かしだします。
この、歯のエナメル質に含まれるカルシウムやリンが溶けだすことを「脱灰(だっかい)」と呼びますが、脱灰が起きても口の中の唾液の中和作用で、溶けだしたカルシウムやリンなどのミネラルが再びエナメル質に戻り、エナメル質を修復していきます。
この歯が修復されるメカニズムは「再石灰化(さいせっかいか)」と呼ばれており、歯は常にこの「脱灰」と「再石灰化」を繰り返しています。
そのため、口の中に虫歯菌が侵入したり、なにかを食べたり飲んだりしても、すぐに歯がむし歯になるということはありません。
しかし、食べ物や飲み物を摂取した後にその食べかすや歯垢が歯に付着したままになっていると、歯のカルシウムやリンを溶かす「脱灰」ばかりが進行するようになり、歯の修復をする「再石灰化」がなかなか進まないようになります。
そのため歯の修復が追いつかなくなり、結果的にむし歯が進行していきます。
むし歯菌に感染した歯は、穴が開くことで象牙質や神経に刺激が伝わり、それが痛みとなります。
子どもの歯は大人の歯に比べて象牙質や神経を守っているエナメル質がとても弱いため、脱灰のスピードが早く、むし歯になりやすい状態となっています。
そのため子どもの歯をむし歯にさせないために、下記の対策を行っていきましょう。
- 食後は歯磨きをしてむし歯の予防をする
- 子どもが自分で歯磨きをした後は、大人が仕上げ磨きをする
- 哺乳瓶で甘いジュースを飲ませたり、だらだら食べをしたりして長時間口の中に食べ物が留まらないように注意する
- 間食の回数が多くなり過ぎないように注意する
- 歯科医院を定期的に受診して口の中の歯垢を除去したり、むし歯にならないようフッ素の塗布をしたりする
- 乳歯のむし歯は進行すると、その下にある永久歯の発育に影響するため、乳歯がむし歯になった場合は放置せずに治療を受ける
以上のようなことを日頃から心がけて、子どもの歯をむし歯から守っていきましょう。
子どもの歯がむし歯にならないようにすることは、子育て中の親御さんにとって常に気になる点だと思いますが、定期健診はどのぐらいの間隔で受ければいいでしょうか。

子どもの歯の健康を守るためには、3ヶ月ごとに歯科医院で定期健診を受けることをおすすめしたいですね。
3ヶ月ごとに定期健診を受けることで、むし歯に早期に対応ができ、大きな問題へと進行するのを防ぐことが可能になるので、抜歯や歯の神経を抜くような重い治療を避けることができるようになりますよ。
3ヶ月の間にむし歯が発見できなかったとしても、むし歯が深刻な事態に進行することはないので、お子さんの口腔内の健康を守るためにも定期健診は必ず受けるようにしてくださいね。

仕上げ磨きに苦労する親御さんたちも多いのではないかと思いますが、仕上げ磨きをする時のコツはなにかありますか。

仕上げ磨きで大切なことは、子どもが自分で磨きにくい場所を大人が重点的に磨くことかな。
例えば、
- 生え変わりでグラグラになった乳歯
- 歯ブラシが届きにくい一番奥の歯
- 上のほっぺたに近い歯(頬側 ⦅きょうそく⦆)
- 下顎の歯の内側(舌側⦅ぜっそく⦆)
- 他の歯と段差がある生えかけの永久歯 とか。
小学校6年生ぐらいまでは仕上げ磨き専用の歯ブラシを使って、大人が仕上げ磨きをすることを推奨しています。
仕上げ磨き専用の歯ブラシは大人が使いやすいように、子ども用の歯ブラシより少し柄が長く、指で押さえやすいようなくぼみがあります。
乳幼児期は長い時間の歯みがきを嫌がるお子さんが多いので、10秒から20秒ぐらいで終わらせれば大丈夫。
でも、歯と歯との間はぜひデンタルフロスを使ってほしいですね。
小学生ぐらいからは、仕上げ磨き専用の歯ブラシやデンタルフロスの他にワンタフトブラシも使って磨くと、磨きにくい奥歯やグラグラの乳歯を磨くときに磨き残しがなくなっていいかな。
グラグラになっている乳歯は磨きにくいかもしれないけど、グラグラしない程度に歯を指で押さえてやさしく磨いてあげれば綺麗に磨けます。
グラグラの乳歯に痛みの刺激があると、永久歯が生えるための指令が脳に出やすくなるので、グラグラの乳歯に痛みを感じるのは悪いことではないんですよ。
歯みがき粉は泡が立ちすぎると綺麗に磨けているか分からなくなってしまうので、泡の立ちにくい低発砲タイプやジェルタイプのものを使うと、磨き残しがないか確認しながら歯みがきができるのでおすすめですね。

歯の生え変わり
子どもの歯が乳歯から永久歯に生え変わる際、歯の痛みを伴う場合があります。
通常、歯が生え変わる際は、永久歯が乳歯の根を吸収しながら成長していき、やがてその根が吸収されてなくなることで、乳歯は歯の頭の部分(歯冠)だけになるため、歯は自然に抜けて痛みを感じることはあまりありません。
では、歯の生え変わりで痛みが生じる場合、どんな原因があるのでしょうか。
萌出性歯肉炎(ほうしゅつせいしにくえん)
萌出(ほうしゅつ)とは、歯が生えてくることを意味しています。
つまり、萌出性歯肉炎とは、歯が生えるときに伴う歯肉炎のことで歯周病の一つです。
乳歯が抜けてから永久歯が生えてくるのに半年ほどかかりますが、永久歯はその間ゆっくりと時間をかけて頭を外に出すようになります。
永久歯が完全に頭を出すまでは、歯肉が断裂され怪我をしているのと同じ状態なので、歯磨きの際に歯ブラシを上手くあてることができずに歯垢が溜まりやすくなり、歯肉が腫れて炎症を起こすことがあります。
これが「萌出性歯肉炎」と呼ばれるもので、歯の生え変わりの際に口の中が清潔に保たれていないと、歯茎が炎症を起こして腫れてしまい、子どもが「歯が痛い」と訴える原因に繋がります。
萌出性歯肉炎になると、子どもはその痛みから食事が上手くできなくなったり、永久歯がむし歯になる原因になったりします。
「むし歯」の解説でも記した通り、幼若永久歯はエナメル質が弱いため、むし歯になりやすい状態となっています。
また、むし歯が神経に到着するまでのスピードも早いため、永久歯のむし歯の進行が急激に進む可能性があります。
萌出性歯肉炎を防ぐためにはお口の中を清潔に保つ必要があるため、歯ブラシのヘッドが極端に小さな「ワンタフトブラシ」などを使って、大人が丁寧に仕上げ磨きをしてあげることが重要になります。
乳歯の生え変わりによる痛み
乳歯が永久歯に生え変わる時、永久歯は乳歯の根っこを吸収しながら発育するため乳歯が歯冠だけの状態になり、ぐらつきがはじまります。
乳歯がぐらつき始めてから自然と抜けるまでに1ヶ月以上かかる場合もあります。
乳歯がぐらつくと、食べ物が噛みづらかったり、歯磨きがしづらかったりと日常生活に支障が出ることがあるかもしれません。
また、乳歯のぐらつきによって痛みが発生することもあります。
乳歯の生え変わりによって歯がぐらついていても、大きな痛みがないようであれば、通常は自然に抜けるまで様子を見ていても問題はありません。
乳歯の生え変わりの時期は下記の通りです。
| 乳歯 | 生え変わりの時期 (上顎) | 生え変わりの時期 (下顎) |
|---|---|---|
| 中切歯 (真ん中の前歯) | 7~8歳 | 6~7歳 |
| 側切歯 (中切歯の隣) | 8~9歳 | 7~8歳 |
| 犬歯 (側切歯の隣) | 11~12歳 | 9~10歳 |
| 第一小臼歯 (犬歯の隣) | 10~11歳 | 10~12歳 |
| 第二小臼歯 (第一小臼歯の隣) | 10~12歳 | 11~12歳 |
また、下記の歯は乳歯からの生え変わりではなく、最初から永久歯として生えてきます。
| 永久歯 | 生え始める時期 (上顎) | 生え始める時期 (下顎) |
|---|---|---|
| 第一大臼歯 (六歳臼歯) | 6~7歳 | 6~7歳 |
| 第二大臼歯 | 12~13歳 | 11~13歳 |
| 第三大臼歯 (親知らず) | 17~21歳 | 17~21歳 |
※上記はあくまでも目安の時期です。実際の乳歯からの生え変わりや永久歯の生え始める時期には個人差があります。
※第三大臼歯の親知らずは生えない人もいます。
歯の根っこがほとんどなくなり、乳歯が歯茎にぶら下がっているようなグラグラの状態であれば、舌で押したり、清潔な指でつまんだりして自分で抜くことも可能です。
しかし、乳歯がぐらついているからと言って早い時期に無理矢理抜こうとすると、歯茎を傷つけたり、歯の根っこが折れたりする可能性があります。
歯茎に傷がつくとそこから細菌が侵入し、歯茎の炎症を起こして歯周病になる恐れがあるため注意が必要です。
乳歯の生え変わりの際、乳歯が下記のような状態にある場合は、お口の中に何らかのトラブルがないか歯科医に相談をしてみましょう。
乳歯のぐらつきの期間が長い
乳歯が大きくぐらついているがなかなか抜ける気配がなく、食事や歯磨きの際に支障があるような場合は、歯科医に抜歯の必要があるか相談をしてみましょう。
乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきている
乳歯が抜けていないのにその内側から永久歯が生えている状態は「二重歯列」と呼ばれ、乳歯の根っこが永久歯に上手く吸収されていないなどの原因で起こることがあります。
乳歯がぐらついて抜ける準備ができているようであれば、二重歯列になっていても様子を見て大丈夫でしょう。
二重歯列は他にも、顎がしっかりと成長していない、顎の大きさに対して歯の大きさが大きいなどの場合に、永久歯の生えるスペースが狭くなり、歯がきちんと並ぶことができずに他の場所から生えてくることがあります。
乳歯がぐらついていないにも関わらず永久歯が生えている場合は、歯磨きがうまくできなかったり、歯並びの問題などが出てきたりするため、歯科医に相談をして適切なアドバイスをもらうようにしましょう。
乳歯が抜けたのになかなか永久歯が生えてこない
乳歯が抜けてから永久歯が生えるまでには3ヶ月ほどの月日がかかります。
これ以上の月日がかかっても問題はありませんが、半年以上経っても永久歯が生えてこない場合は下記のような原因が考えられるため、歯科医に相談をしてみましょう。
| 原因 | 症状 |
|---|---|
| 顎が小さい | 顎が小さく永久歯の生える隙間がないと、永久歯が生えてこないことがある |
| 永久歯の先天性欠如 | 永久歯の元となる歯胚が最初から作られていないことが原因で永久歯が生えないことがある |
| 埋伏歯(まいふくし) | 顎の骨や歯肉の下に永久歯が埋まってしまい、永久歯が生えてこないことがある |
上記のような場合、レントゲン撮影をすることでその原因を発見することができます。
いつまでも歯がない状態で過ごすと、歯並びや噛み合わせが悪くなったり、歯磨きがうまくできずに歯周病になったりする可能性があります。
永久歯がなかなか生えずに心配があるようであれば、歯科医院を受診し、適切なアドバイスをもらうようにしましょう。
乳歯が大人になっても抜けない
12~13歳ごろになると全ての歯が乳歯から永久歯に生え変わりますが、時々、乳歯が生え変わらずに大人になってもそのまま乳歯が残る場合があります。
このような歯を「大人乳歯」と呼びますが、大人乳歯は子どもの乳歯と変わりがないためエナメル質が弱く、むし歯になりやすい状態となっています。
大人になっても乳歯が抜けない原因として、先ほど紹介した「永久歯の先天性欠如」などが考えられます。
日本小児歯科学会が2010年に発表した調査結果(日本人小児の永久歯先天性欠如に関する疫学調査)によると、10人に1人の子どもに永久歯の先天性欠如があると報告されています。
永久歯の先天性欠如が原因の場合、大人乳歯を抜歯しても永久歯は生えてこないため、そのまま様子を見たりしますが、大人乳歯は永久歯に比べてむし歯になりやすいだけでなく、歯の大きさが小さいため歯並び悪くなることがあります。
歯並びが悪いと、見た目が悪くなったり、噛み合わせや歯磨きにも影響したりするため、この場合も、歯科医から適切なアドバイスをもらうようにしましょう。
知覚過敏
「アイスクリームなどの冷たいものを食べると歯にしみて痛い!」と感じるような症状が、この「知覚過敏」です。
知覚過敏は大人だけではなく、子どもにも起こる症状の一つです。
知覚過敏は冷たいものなどの刺激が歯の神経に伝わることで痛みを感じるようになるため、エナメル質の薄い乳歯は知覚過敏を起こしやすい歯だと言えるでしょう。
強い力で歯磨きをすると、薄いエナメル質が摩耗したり、歯茎が退縮(縮小)したりして、知覚過敏が進行する恐れがあります。歯磨きをする際は、歯茎が傷つかないよう柔らかい歯ブラシで優しく磨くことを心がけましょう。
口内炎
子どもの口の中に口内炎ができた場合にも、子どもは「歯が痛い」と訴える時があります。
一般的にみられる口の中にポツッと白いニキビのようなできものの口内炎は「アフタ性口内炎」と呼ばれ、通常は1〜2週間で自然治癒します。
アフタ性口内炎は
- ビタミンなどの栄養不足
- 睡眠不足
- 歯磨きや歯並びなどの矯正歯科治療の器具によってできた傷
- 口の中の火傷
- 口の中の細菌の繁殖
- 免疫力の低下
- ストレス
などが原因で発症することがあります。
口内炎は、小児科や小児歯科で薬をもらうことが可能です。
口内炎を防ぐためには、バランスの良い食事をこころがけ、口の中を清潔に保つようにしましょう。
また、痛みがひどく熱がある場合は「ヘルペス性口内炎」や「ヘルパンギーナ」などのウイルス性の口内炎の可能性があります。
口内炎が2週間以上治らないような場合は、一般的なアフタ性口内炎ではない可能性があるため、小児科などを受診し、治療を受けるようにしましょう。
中耳炎
中耳炎になると耳や頬の辺りに痛みを感じるようになります。
そのため、そこに近い奥歯などが痛いような気がして、子どもが「歯が痛い」と言う時があります。
お口の中に何もトラブルが見つからないようであれば中耳炎に罹っていないか疑い、発熱や耳の痛みの有無を確認の上、判断が難しいようであれば小児科の医師に相談してみましょう。
歯の痛みの原因2:事故やケガ
子どもが歩き始める1歳から3歳ごろや、活動が活発になりだす8歳から10歳ごろは、転倒して口の中のケガが多くなる時期です。
歩き始めたばかりの年齢の子は体よりも頭の方が重いので、バランスを崩してテーブルの角に顔をぶつけたり、椅子や階段などの高い場所から落ちて転倒したりします。
小学生以上になれば、活発にスポーツをするようになったり、走って友達とぶつかったりしてケガをすることも多くなってきます。
このように、事故やケガなどが原因でお口の中がダメージを受けて、歯が欠けたり、抜けたりして子どもが「歯が痛い」と訴えてくることがあります。
まずは落ち着いてお子さんの口の中の状況を確認し、事故やケガなどの原因で歯の痛みがある場合、どのように対処すればいいのかその方法を見ていきましょう。
歯が抜けた場合
歯が抜けた場合、歯が抜けてすぐであれば「再植(さいしょく)」という方法で治療をすることで、再度歯を元に戻して使えるようにできる可能性があります。
その場合、歯の根っこの部分にある「歯根膜(しこんまく)」を生かす必要があるため、抜けた歯は冷たい牛乳か、歯を保存する専用の保存液につけて歯科医院まで持っていくことが大切です。
牛乳は手に入りやすいだけではなく、浸透圧が生体に近い滅菌水として歯の保存に有効に活用できます。冷たい牛乳に入れておくと、歯根膜を6〜12時間ほど生かしておくことができるので、専用の保存液がない場合は牛乳で代用が可能です。
ただし、牛乳アレルギーがある子どもには使用ができませんのでご注意ください。
もしも、保存液が手元になかったり、牛乳アレルギーがあるような場合は、生理食塩水を使用するか、あるいは塩分濃度が0.9%の食塩水(500㎖の水なら4.5gの塩を入れたもの)をミネラルウォーターや煮沸済みの冷めた水などで作って、その中で抜けた歯を保存するにしましょう。
抜けた歯を真水に入れて保存すると、浸透圧の違いから歯根膜を長く生かすことができません。
また、抜けた歯を30分以上乾燥した状態で放置すると、歯根膜が死んでしまう可能性があるため、必ず冷たい牛乳や食塩水などの中に入れるようにしましょう。
事故やケガなどが原因で歯が抜けたとしても、歯根膜が生きた歯をすぐに治療すれば、再度元に戻して使えるようになる可能性があるなんてすごいですね。
再植後は今までと同じように歯が使えるようになるんですか。

抜けてしまった歯の歯根膜を保護するのに一番いいのは、生理食塩水などの等張液(とうちょうえき)ですね。
ただ、皆さんに覚えておいてほしいのは、歯の再植ができたとしても、抜ける前と同じ状態で歯根膜は機能しないということなんです。
再植した歯の周りの歯根膜は時間が経つにつれて元の機能を失い、骨性癒着(こつせいゆちゃく)と言って、歯は歯槽骨(しそうこつ)と歯のセメント質が直接くっつく(嵌合:かんごう)ことで固定されます。
ただし、この状態で固定された歯も、時間が経つと周囲の骨との結合が弱まり、将来的に抜ける可能性があります。

歯が折れたり欠けたりした場合
歯が折れたり欠けたりした場合でも、再度歯を接着して元に戻すことができるケースがあります。
そのため、歯が抜けた場合と同様に、折れたり欠けたりした歯を冷たい牛乳や食塩水などの中にいれて歯科医院に持っていくようにします。
もしも、再度歯を接着することが難しいようであれば、欠けた範囲にもよりますが、その部分をコンポジットレジンと呼ばれる歯科用の樹脂やセラミックなどで修復をするようになります。
歯がぐらついている場合
歯のぐらつきがそれほど大きくない場合は、噛み合わせを確認後、歯科医の判断で経過観察をして様子を見ることができます。
ただし、ぐらつきが大きい場合は歯の根っこが折れたり、歯が固定されている骨から離れる脱臼の状態になったりしている恐れがあります。
その場合は、ぐらついている歯を両端の歯で固定して状態を経過観察したり、歯の根っこの治療をしたりします。
歯の色が変わった場合
歯の色が変わった場合は、歯の神経が損傷して内出血を起こしている可能性があります。
この場合は、日数の経過とともに自然治癒することもあるので、レントゲンなどで状況を確認後、経過観察をします。
ただし、日数が経過しても変色が続くようであれば、歯の神経が壊死している可能性があり、歯茎が腫れたり膿を持つようになる恐れがあるため、歯の根っこの治療が必要となります。
これらの症状を治療せずに放置すると、永久歯への生え変わりに影響を与える恐れがあるため、きちんと歯科医院で診療を受け、適切な処置をするようにしましょう。
歯の位置がずれた場合
歯が衝撃で歯茎の中にめり込んだり、傾いたりした場合も、レントゲンを撮って歯の状態を確認します。
乳歯であればそのまま経過観察をすることもありますが、位置がずれた歯が永久歯であれば、歯を矯正する装置で歯を引っぱり元の位置まで戻して固定したりします。
歯に痛みがある場合の応急処置
口の中にトラブルが起きたり、事故やケガなどで歯に何らかの損傷があったりする場合は、歯科医に相談をして適切な処置を受けることが大切です。
しかし、歯科医院に到着するまでの間、歯茎から出血したり、子どもが痛みを訴えたりする場合もあります。
そのような場合、まずは下記のような応急処置を施しましょう。
状況別応急処置1:出血
口の中が何らかの理由で損傷した場合、唇や頬の内側、歯茎などから出血をする場合があります。
出血が多かったり、口の中に砂などが入っていたりする場合は、うがいをして口の中を清潔な状態にします。
その後、確認できた出血部分の患部を清潔なハンカチやガーゼなどで強く圧迫して出血を止めるようにします。
通常の出血であれは5〜10分ほどの圧迫で止血するので、患部の圧迫は出血が止まるまで続けるようにしましょう。
状況別応急処置2:歯茎の腫れ
歯茎が腫れているような場合は、その腫れた部分を氷を包んだタオルや保冷剤、冷却ジェルシートなどで冷やすようにします。
この場合、腫れている患部に直接氷をあてるのではなく、頬の上から冷やすようにしましょう。
状況別応急処置3:歯痛
歯や歯茎に痛みがあるような場合は、小児用の鎮痛剤などの薬を服用します。
むし歯などで突然歯が痛くなったような場合でも、鎮痛剤を服用することで痛みが和らいだりします。
市販の鎮痛剤を服用する場合は必ず服用方法を守り、小児用を飲ませるようにしましょう。
歯の痛みがある場合にしてはいけないこと
歯の痛みがある場合に、こんなことをすると痛みが増幅するかもしれないという内容をご紹介します。
してはいけないこと1:痛みのある患部を手で触る
バイ菌がついた手で痛みのある患部を触ると、その部分が汚染されて痛みが増幅する恐れがあります。
痛みがある場合はなるべくその患部は触らずに、冷やしたり、小児用の鎮痛剤を服用するなどして応急処置をするようにしましょう。
してはいけないこと2:熱い・冷たい・硬い食べ物を食べる
熱いものや冷たいものを食べると患部が刺激されて、痛みが増幅する恐れがあります。
また、硬い食べ物が歯と歯の間に挟まった場合も、患部が圧迫されて痛みが増幅する恐れがあります。
食事をする時は、なるべく常温の物や歯に挟まりにくい柔らかい物を食べるようにしましょう。
してはいけないこと3:激しい運動や入浴
激しい運動をしたり、熱いお湯につかって入浴をしたりすると、血行が促進されて痛みが増幅する恐れがあります。
歯の痛みがある時は、なるべく激しい運動や熱いお湯での入浴を避け、安静にするようにしましょう。
してはいけないこと4:痛みの放置
歯が痛いにも関わらずその痛みを放置すると症状の悪化に繋がり、さらに痛みを増幅させる恐れがあります。
歯の痛みがある場合、歯科医院を受診して痛みの原因を探り、適切な処置を受けるようにしましょう。
まとめ
お子さんから「歯が痛い」と言われると心配になるかもしれませんが、早めにその原因を探り、対処や治療をすることで症状の悪化を防ぐことができます。
特に事故やケガなどで歯が損傷すると心配になってオロオロとしてしまうかもしれませんが、事前に対処法を確認しておくことで落ち着いて行動ができるようになります。
折れたり欠けたりした歯は牛乳や食塩水の中にいれて歯科医院に持っていくことを覚えておくだけでも、いざという時に落ち着いて行動をとることができるかもしれません。
子どもの歯の痛みの原因にはさまざま原因があります。
普段からお口の中を清潔に保ったり、対処の方法を確認したりして子どもの歯の痛みに対する対策をとるようにし、子どもが「歯が痛い」と訴える場合は早めに歯科医院を受診して治療を受けるようにしましょう。